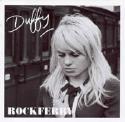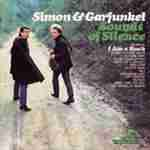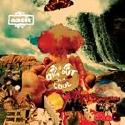
結成14年目、
“バンド”oasisの誕生を謳う1枚
僕がoasisのCDを最初に買ったのは、
世界中で驚異的に売れた彼らの2ndアルバム『Morning Glory』(95年)だった。
当時高校1年生だった僕は、少し背伸びをして、ちょっとずつ「洋楽」というものを聴き始めた頃だった。
その頃クラスで人気があったのは、BonJoviやMr.Bigといったアメリカのポップメタルバンドばかりだったので、
洋楽のロックといえば、ギターはいかにもエレキという風に尖った形(ストラトタイプ)をしていて、
音はキュイーンと高めに歪んでいて、長髪で、メイクをしていて、
革ジャンや派手な衣装を着ているイメージしかなかった。
そんな僕の目に、oasisは最初、かなり異様に映った。
使っているエレキギターは丸みのある形(エピフォンやテレキャスター)をしているし、
音はズゥゥンとやけに重いし、髪は短いし、着ている服は普通のシャツやジャケットだった。
けれど、曲はインパクトがあった。
ノエル・ギャラガーの書くメロディはクリアで聴きやすいのに中毒性のある独特の節があって、
それを歌うリアム・ギャラガーの声は無機的なのに粘っこくて耳に残った。
何よりリアムの、あの死んだ魚のような目をしながら歌う姿が強烈だった。
髪を振り乱しながら超人的な速さでギターを弾く、そんなパフォーマンスこそがロックだと思っていたのに、
俯きながらギターを弾くoasisの方がずっとかっこよかった。
思えば、ブリティッシュロックへと通ずる道へと僕を導いてくれたのはoasisだった。
外見や派手なパフォーマンスではなく、初めて音でロックスピリットを感じさせてくれたのも、
ビートルズでもストーンズでもなく、oasisだった。
だが僕はその後、oasisの熱心なリスナーではなかった。
oasisを追い続けることよりも、未知のバンドを知ることの方に夢中になったからだ。
U2やR.E.M.といった、よりクセのあるバンドの方が魅力的に見えたし、
70年代、60年代と遡れば、それこそかっこいいバンドは星の数ほどあった。
そんな時期の僕にとっては、3枚目の『Be Here Now』も4枚目の『Standing On The Shoulder Of Giants』も、
単に『Morning Glory』の焼き直しに聴こえた。
昨年、ベストアルバム『Stop The Clocks』をリリースした時も、
「ついにベストを出すほど落ちぶれたか」とネガティブな気持ちにすらなった。
新作『Dig Out Your Soul』を聴いたのは、
「久々にちょっと聴いてみるか」という、ほんの気まぐれからだった。
だが、1曲目の「Bag It Up」から圧倒された。
クールに刻むドラムにリアムの声が加わり、徐々にギターの厚みが増していく。
そして、コーラスパート前のブリッジ部分で、それまで静かだったメロディが、
押し殺していた興奮を開放するかのように一気にピッチを上げて、リアムが乱暴に叫ぶ。
このあたりのメロディとハーモニーは、いかにも「ノエル節」だ。
全曲通して強く感じるのは、ギター以外の音の存在感だ。
特にドラムが重く、乾いていて、爽快なグルーヴを生み出している。
相対的にノエルのギターは一歩下がった形になるが、
それでも全ての曲は、紛れもなくoasisの曲になっている。
これまでは、ノエルのギターとリアムのボーカルによって支えられてきた感があるが、
ここにきてoasisという「バンド」のサウンドができあがったようだ。
だがそれは、彼らが結成14年を経て得た円熟などではなく、
むしろその逆で、よりバンドらしいバンドへと進む第1歩のように見える。